年次有給休暇の時季指定義務
記事作成日:2025/3/31
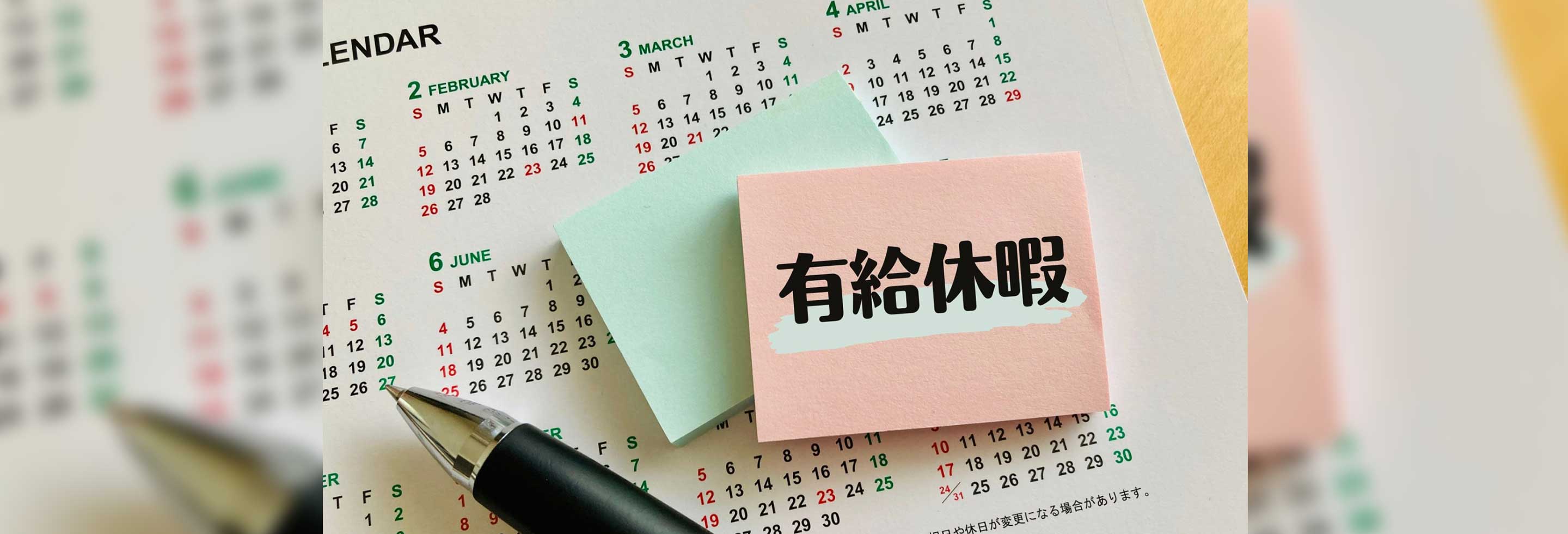
年次有給休暇は、労働者が心身ともにリフレッシュできることを目的として労働基準法で定められた制度です。
事業主は、一定の要件を満たした労働者に対して、毎年一定の日数の年次有給休暇を与えることが定められています。
しかし、実態として自発的に労働者が有給休暇を取得できるような環境が整備されている企業が少なかったため、2019年4月の労働基準法改正により年次有給休暇の時季指定義務が定められました。
年次有給休暇の時季指定義務とは、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に年5日間の有給休暇を取得させることを義務付けたものです。
今回は、年次有給休暇と年次有給休暇の時季指定義務について解説していきます。
年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた一定の条件を満たした場合に所定の日数の有給(給与が支払われる)休暇の付与を義務付けている制度のことです。
労働基準法では、以下の条件をいずれも満たした場合に年次有給休暇を付与しなければならないとしています。
・雇い入れ日から6か月が経過していること
・その期間(2回目以降は最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日)の全労働日の8割以上出勤したこと
年次有給休暇の付与条件を満たした場合、年次有給休暇は以下の日数分が付与されます。
| 雇入れの日以降起算した勤続期間 | 付与される有給休暇の日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10労働日 |
| 1年6か月 | 11労働日 |
| 2年6か月 | 12労働日 |
| 3年6か月 | 14労働日 |
| 4年6か月 | 16労働日 |
| 5年6か月 | 18労働日 |
| 6年6か月以上 | 20労働日 |
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れ日以降起算した継続勤務期間(年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||
| 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
有給休暇の時季指定義務とは、年次有給休暇の取得率が低調であり、年次有給休暇の取得促進を目的として2019年4月の労働基準法改正により定められた制度です。
この制度により、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、年5日間の年次有給休暇を必ず取得させることが、すべての企業において義務付けられたのです。
年次有給休暇は労働者自らの請求した時季に与えることが原則ですが、取得率が低いなどの問題がありました。
この法改正により、年次有給休暇を付与した基準日から1年以内に5日について、使用者が労働者の意見を聞いた上で使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
年次有給休暇の時季指定義務対象者は、正社員、パート、アルバイトなどを問わず年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。
労働者自らが請求して取得した年次有給休暇の日数や、労使協定に定められた計画年休のため与えた年次有給休暇の日数は、その合計日数分を時季指定義務の年5日から控除することが必要です。
例えば、労働者が既に年次有給休暇を自らの請求で2日間取得していた場合は、時季指定義務による年次有給休暇の取得は3日間になります。
時季指定義務により労働者に年次有給休暇の取得をさせる場合には、労働者の意見を聞いてできるだけ希望通りの時季を指定しなければなりません。
時季指定義務を企業などが守らなかった場合には、労働基準法違反により30万円以下の罰金が科される可能性がありますので注意が必要です。
労務関係につきまして知りたいことや疑問点などがございましたら、是非一度当事務所にご相談ください。